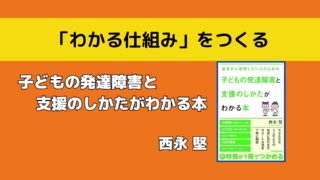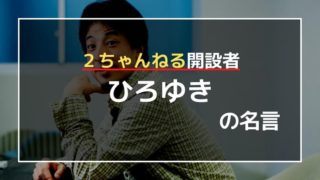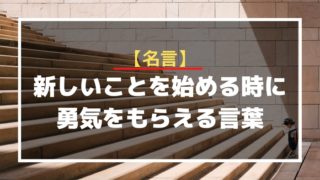「問題行動」を“学びの途中”として見直す一冊
子どもは、発達障害によって、ほかの子が自然に習得することをなかなか身につけられないから、問題行動を起こしてしまうのです。
この言葉は、本書全体を貫く前提だと感じました。
問題行動を「性格」や「わがまま」で説明するのではなく、まだ獲得できていないスキルの表れとして捉える。
この視点に立つことで、対応は「叱る・止める」から「教える・支える」へと自然に変わっていきます。
子どもの行動が荒れて見えるときほど、実は「わからない」「できない」状態に置かれています。
まずその理解に立ち戻ることが、すべての支援の出発点なのだと改めて感じました。
正解を教えるより、「自分で気づく」余地を残す
「注意」「指導」ではなく、「気づかせてあげる」ほうがいいのです。
では、どう関わればいいのでしょうか。
本書が示しているのは、大人が正解を与えるのではなく、子ども自身が気づけるように導く関わりです。
そのために重要なのが、穏やかさ、距離感、タイミング。
感情が高ぶっている子に正論をぶつけても、学びは起こりません。
まず安心できる状態をつくり、そのうえで「自分で気づく余地」を残しましょう。
この姿勢が一貫して語られている点に、本書の実践的な価値を感じました。
ほめるとは、「次の行動」を育てること
ほめるときには、同時に必ず、身につけてほしい『望ましい行動』や『スキル』を子どもに伝えなければ、十分な支援にはなりません。
本書の「ほめる」は、単なる承認やご褒美ではありません。
次に同じ行動を選べるようにするための情報提供です。
だからこそ、
すぐに、具体的に、言葉にする
という原則が大切にされています。
「えらいね」ではなく、「今、静かに待てたね」「目を見て聞いてくれたね」。
こうした声かけは、子どもにとって行動の地図になります。
また、「理想に近づけるために、何をほめるのか」という視点をもつことが大切です。
この視点を持つと子どもの行動に見え方が変わってきます。
これらの転換こそが、子どもの伸びを支えていくのだと思います。
まとめ
この本は、声かけのテクニック集ではありません。
子どもの行動をどう理解し、どんな立場で関わるかを静かに整えてくれる一冊です。
問題行動を減らすことが目的なのではなく、
次にどうすればいいかを、子ども自身が選べるようになることを目指しています。
そのための視点と具体性が、過不足なく詰まった本だと感じました。
発達障害の子どもと関わる人にはぜひ読んでもらいたい1冊です。
この本の詳細はこちらからどうぞ。