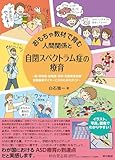1.“遊び”が、子どもと心をつなぐ最良の教材だった
「おもちゃ」と聞くと、どうしても“遊び”という軽いイメージを持たれがちです。
ですが、本書『おもちゃ教材で育む人間関係と自閉スペクトラム症の療育』(白石雅一著)は、まさにその“遊び”こそが、発達支援における最も深い学びであることを教えてくれます。
2.子どもの発達を「心の理論」から見つめ直す
著者はまず、発達の節目として「心の理論」を丁寧に説明します。
4歳頃に「相手の立場を考えること」ができるようになり、5歳頃には仲間意識が育ち、集団での遊びが増える
この自然な発達の流れに基づき、“人と関わる力”をどのように支援すべきかを明快に解説しています。
つまり、「療育」とは“特別な訓練”ではなく、発達の流れに沿って、心を通わせながら社会性を支える営みなのです。
3.ASD児への支援は「情動調律」がカギ
本書の中で特に印象的だったのが、「情動調律」という考え方。
ASDの子どもが感情の乱れを見せたとき、支援者はまず「同調」し、次に「調律」し、最後に「調整」する。
つまり、大人の側が子どもの心のリズムに合わせていくというアプローチです。
“落ち着かせよう”ではなく、“一緒に落ち着く”という姿勢。
この視点を持つだけで、支援の質が大きく変わると感じました。
4.「見通し」と「安心」が、挑戦する力を生む
「やって欲しいこと」や「どうやって行うのか」「どこまでやったらおしまいになるのか」を事前によく説明をして、かつ、「やり方の手本」や「行った後の完成品」も見せて、「見通し」と「安心」と「動機づけ」をもたせて、課題に応じてもらいます。
この一文には、現場支援の核心が詰まっています。
見通しがあるからこそ、子どもは“頑張ってみよう”と思える。
それは私たち大人も同じです。
5.おもちゃ教材×個別療育=信頼関係を育てる時間
白石氏は、一日のうちに15〜30分間の個別療育時間を設けることを推奨しています。
その短い時間に、あいさつ→課題説明→タイマーで時間提示という明確な流れを持たせる。
この一貫した構造が、子どもの安心感を育てるのです。
6.指示より、やさしい「関わり」を
著者は、ASDの子どもが「見て」「やって」「待って」と言われたとき、それを侵入行為のように感じることがあると指摘します。
だからこそ、「平気だよ」「怖くないよ」「すぐ終わるよ」といったクッション言葉を添えることが大切だと説きます。
これは、療育に限らず、すべての対人支援に通じるコミュニケーションの極意だと感じました。
まとめ:療育とは、関係を“つくる”こと
この本を通して感じたのは、療育の本質は“教えること”ではなく、“関係をつくること”だということです。
おもちゃ教材という身近なツールを使いながら、子どもの心に寄り添う、その繰り返しが、発達支援の原点なのだと思います。
白石氏の言葉には、理論だけではなく、現場で子どもたちと向き合ってきた経験から滲み出る温かさがあります。
だからこそ、この本は「どう関わるかに迷ったときの指針」として、多くの支援者の手元に置いておきたい1冊です。
『おもちゃ教材で育む人間関係と自閉スペクトラム症の療育』は、「支援のやり方」ではなく「支援者のあり方」を教えてくれる本です。
子どもと向き合うすべての人に、ぜひ読んでほしい1冊です。